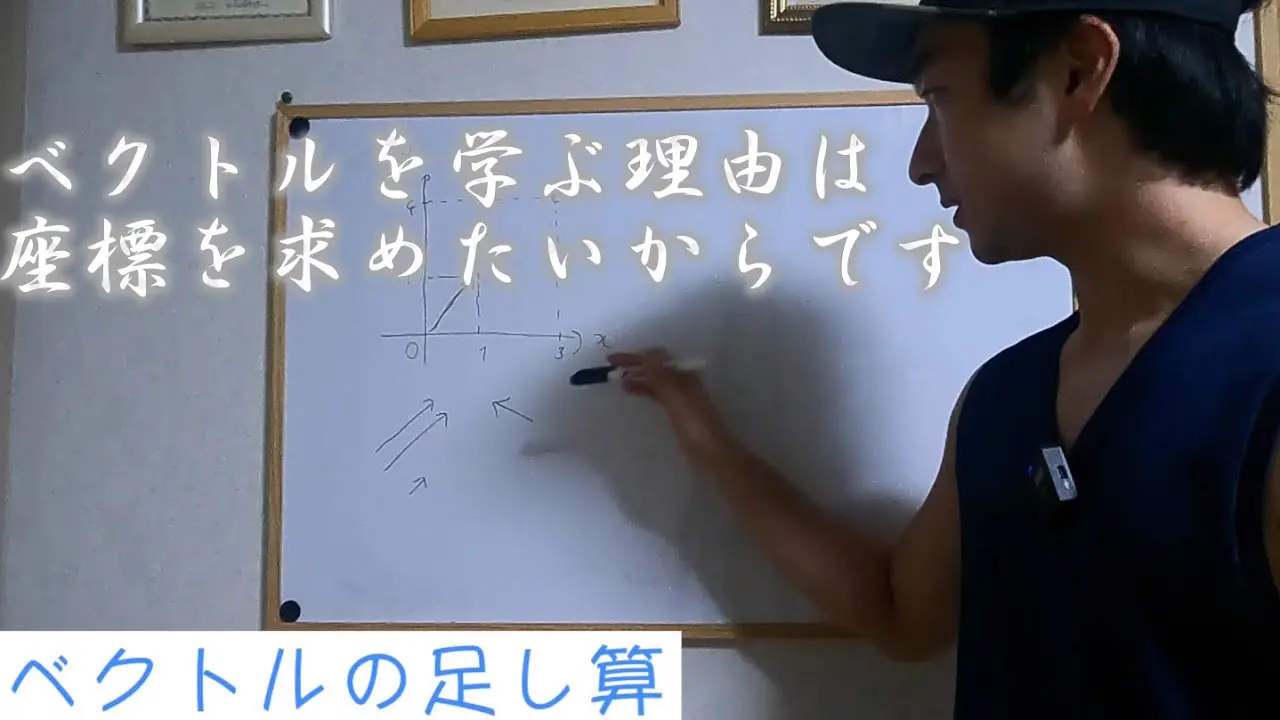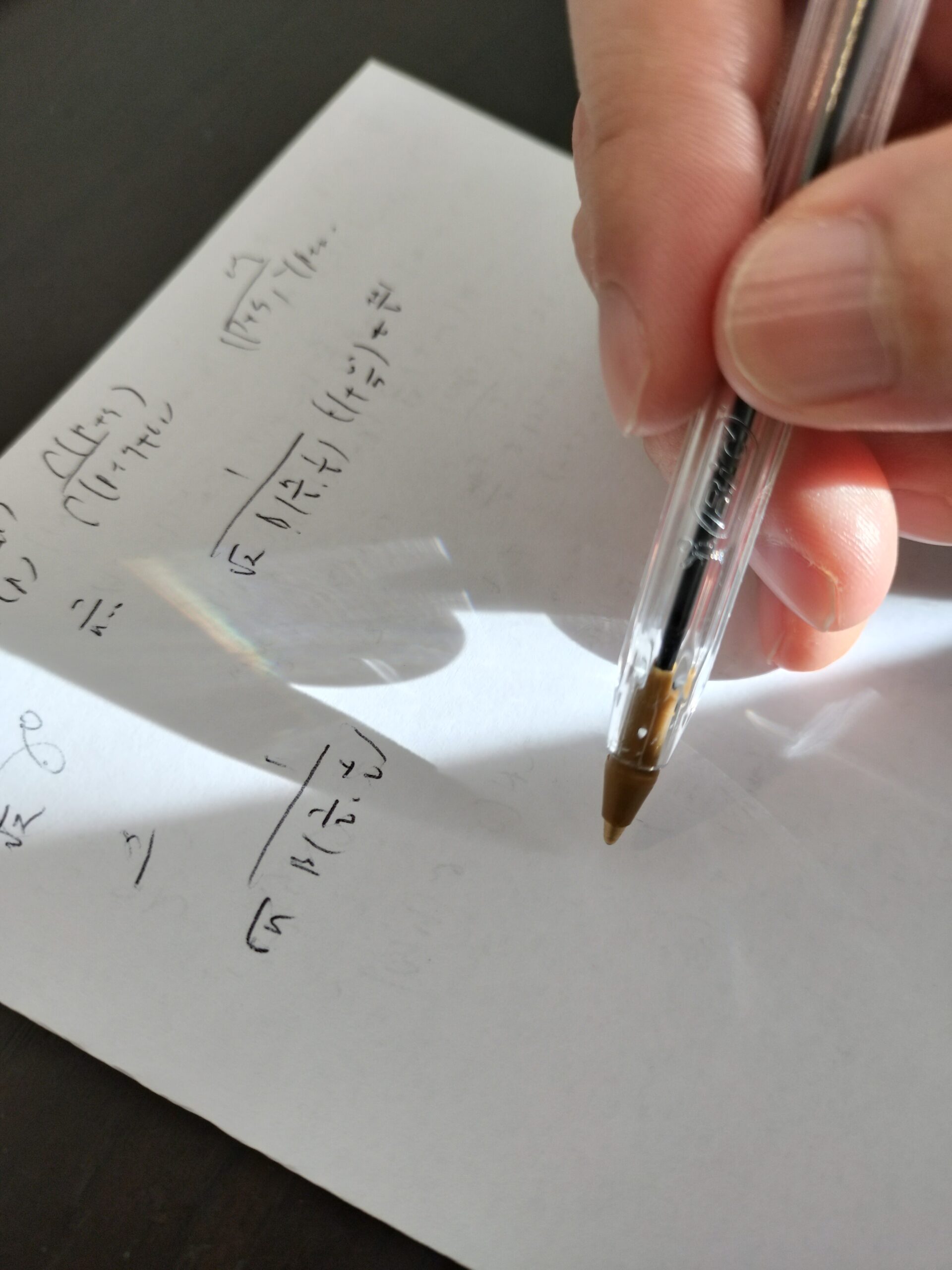この記事は過去に書いた記事を最新の情報でお届けいたします。
数学検定2級に合格するための勉強法を解説します。
数学検定2級は数年前と比べて検索ワードが細かくなっており、中学生という言葉が見受けられるようになりました。
大学受験の半数が推薦で合格している現代では資格試験の需要が高まっているのですね!
中学生の頃に数検2級に合格した経験をもとに、何歳であっても数学検定2級に合格できる必勝法を伝授したいと思います。
1冊の本をメインに取り組めば合格できます!
それでは目次をご覧ください!
数検2級の難易度レベル(合格率)や日程について
数学検定2級の範囲は高校2年生までに学習する内容です。
合格率は毎回3割程度に落ち着いています。
高校2年生といえば、文系数学の範囲ですが、ここら辺から数学に苦手意識を持つ生徒が増えてきます。
数学検定協会もそこは理解しているので、合格率が30%といえどもつまずいてしまう分野が多いと合格することは難しくなります。
数学検定2級は問題数が準2級と比べて減りますよね?
1問1問の重みが上がってくる感じです。計算ミスはなんとしても防ぎたいですね。
数検2級から2次で選択問題形式が導入されます。この傾向は数学検定準1級や数学検定1級へと引き継がれます。
苦手分野を払拭していくことが数学検定2級合格への近道です。
苦手分野を克服する基準は共通テストなどの問題を解けるという意味でなく、教科書の例題程度の問題を解けるようにするという意味です。
特に大学入試を意識している方や、数学検定準1級以上を目指していく方は、数検2級の内容が万全だとかなり有利となります。
日程については数検2級は個人受験の場合は年に3回行われております。
団体受験の場合は、学校によって回数が決まっています。
たくさん受験の機会が欲しい時は、仲間を募って先生に「お願いします!」と頼んでみましょう。
数検2級の過去問と参考書のおすすめ(範囲も紹介)高校生の合格率が高い理由
数学検定2級は『合格ナビ』だけで合格可能です。
本書の特徴は何と言っても質の高さです!分野ごとに過去問ベースに内容が構成されています。思考法も学べるので2次合格もこれ一冊で養えます。
つまり過去問を購入する必要がまったくないということです!
僕が受かったのは中学生の時でした。当時はこのような質の高い参考書がなく複数の書籍を頼りに勉強していました。
『合格ナビ』はベクトルなど苦手な方が多い部分を丁寧に説明してくれているので、初見状態の方でも理解しやすい構成になっています。
本書の目次をご覧になってください!頻出部分が明確にわかります!
厳密には数学検定2級では数学Ⅰ、数学A、数学Ⅱ、数学Bの4冊が必要です。
大学入試の数学の参考書をしっかり行うことは素晴らしいですが、数学検定2級に合格するためにはオーバーワークになります。
そのため高校生が数検2級を受けるとほとんど合格できる(はず)ので合格率が高くなります。
数検2級に合格するためにはそこまでの難しい参考書に取り組み必要はまったくありません!
勉強法についてなのですが、どの分野を重点的に行うべきですか?
数検準1級なども考えている方は三角関数とベクトルです。
指導経験上では超上位校を除き、高校2年生で三角関数で数学が苦手になり、ベクトルの理解が疎かなため入試問題が解ききれない現象が起きます。
この現象は少なくとも15年程度は続いており、
数学検定協会もそれを理解しているからか、この2分野の問題は数検準1級や数検1級の上位級でも頻繁に出題されます。
三角関数は加法定理以外は導き方も覚えておくと公式を忘れにくい状態になります。加法定理の証明は難しいので個人的には最後にやるのが良いと思います。ベクトルは平面・空間を区別せずに、点の座標を求めるためにベクトルを用いているという認識を持ちましょう。
これができなくても数学検定2級には合格できますが、合格するならば本質的なことを理解した状態が良いですよね!
個人的にベクトルはかなり好きな分野でベクトルの実力を本格的に伸ばしたい方におすすめです。
数検2級にはオーバーワークですが、数検準1級や大学入試を意識していてベクトルが根本的から苦手な方におすすめしたいです!
もちろん中学3年生の範囲や高校1年生の範囲も出るのですが、
『合格ナビ』にはそれらの復習も入っているので、中学生でも必ず合格できます。頑張ってください!