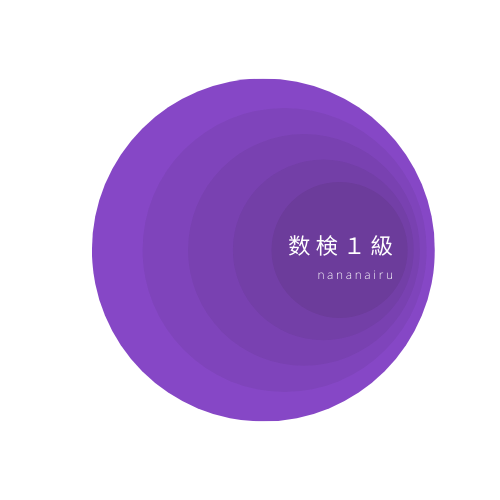受験数学の参考書といえば、なんですか?


などと論争が起こりそうですね笑
青チャートは有名な和田秀樹さんが提唱されてより人気になったように思います。
僕も青チャートは面白い本であると思っていますが、やはり欠点もあるのが実情です。
もちろん分野として最適というかベストな分野もありますので、こう言った内容を紹介したいと思います。
青チャートの欠点は量が多すぎること?
枕にできるぜ!
このセリフを以前、何度生徒から聞いたことか・・・笑
まず青チャートって分厚いのです。
これは現行過程の本ですが、僕は学生の時に数学の先生からタダでもらいました。
「これで数検2級の勉強しなよー」と。

-

-
【数学検定2級】難易度は合格率30%!文系数学範囲レベルの過去問の勉強時間や参考書と問題集の勉強法について解説
続きを見る
あくまでも青チャは受験数学のための本です。

青チャートの欠点
- 基礎問題が多い→教科書の例題レベルが多すぎて本質が見えなくなっている章がある
- 章末問題がやけに難しいw→例題だけ回せばいいんじゃないのか
ということで僕が思うこの欠点というより非効率な面を極限にまで省いたのが1対1対応の演習シリーズです!
1対1対応の演習はやはり受験数学の標準的な参考書だった!
1対1対応の演習は現在、受験数学で難関大学を目指す人には欠かせないツールになりました。
-

-
1対1対応の演習を夏休みに一気に仕上げるための学習スケジュール!
続きを見る

-

-
場合の数・確率ってどんな参考書がベストなの?→ハッ確と合格る確率
続きを見る
数学の分野で青チャートの方が1対1対応の演習よりもオススメな分野を紹介!
では、いよいよ各分野ごとを見ることによって青チャートを使った方が理解のしやすさが良いと思われる分野を紹介します!
数学Ⅰ
- 数と式→1対1対応の演習
- 二次関数→1対1対応の演習
- 三角比→1対1対応の演習
- データの分析→青チャート
データの分析は1対1対応の演習では問題が少ないからです!
数学A
- 場合の数→青チャート
- 確率→青チャート
- 整数→1対1対応の演習
- 平面図形→1対1対応の演習
確率などは青チャートの方が立式の前の思考法がわかりやすいからです!
数学Ⅱ
- 式と証明→1対1対応の演習
- 複素数→1対1対応の演習
- 三角関数→1対1対応の演習
- 指数対数関数→1対1対応の演習
- 微分積分→1対1対応の演習
結論は全て1対1対応の演習です。
青チャートはこの数学Ⅱが分厚すぎるのが最大の欠点です!
数学B
- 数列→青チャート
- ベクトル→1対1対応の演習


数学Ⅲ
- 分数関数無理関数→1対1対応の演習
- 二次曲線→1対1対応の演習
- 複素数平面→1対1対応の演習
- 微分積分→1対1対応の演習
1対1対応の演習で掲載例題の質が最も高いのが数学Ⅲの本です。
是非とも参考になさって、頑張ってくださいね!
青チャートも全部ではなく、分野や使用法をしっかりと考えて使えば最高の本となります!
それは昔も今も変わらない真実です。